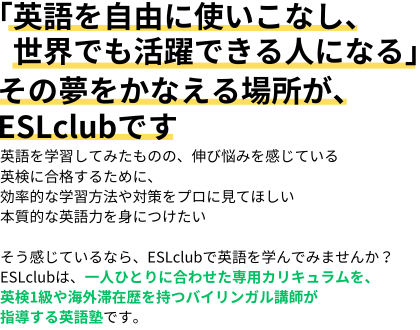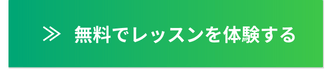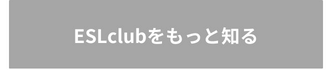「こどもに英語の本を読ませたい」、もしくは「洋書を読めるようになりたい」というきっかけで本を買おう思ったとき、本屋さんに行ったりネットショッピングしたり、という方が多いはずです。
しかし本やサンプルを目の前にして、「果たしてどの本から読み始めたらいいんだろう、、、」なんて悩んでしまうことはありませんか。
また、本を買ったものの、「本当にこの本で良かったの?」と不安になることも少なくないと思います。
今回は、「本屋さん」に行く前に、オンラインショップで「購入確定ボタン」を押す前に
ご家庭で「読む力」に見当をつけることができ、買うべき「本の難易度」を知ることができる方法を3つご紹介します。
1. Lexile指数 (Metametrics社)
2. YL (SSS英語多読研究会)
3. DRA (Learning A-Z)
※かっこ内は開発した組織名。
これらを活用することで、現在の「読む力」と、「読む力に合った英語の本」が見つかるでしょう。
こちらもあわせてご覧ください
1. Lexile指数とは?
学習者の読解力向上を目的に開発したオンラインプログラムで、多くの学習者と本や記事とを結びつけています。
世界165カ国以上で使われており、アメリカでは小学生?高校生がテストを受けてその読解力を表す指標としています。
Lexile指数は、「読解力」と「英文の難しさ」を表しており、それぞれを200L?1700Lという数値で表されます。数値が低いほど、学習者だと「読解力」がない、英文だと「易しい」という判断になります。
日本では、Amazon.co.jpのサイト内に「Lexile指数別サンプルテキスト」という、英語レベルにあった本を選べるページがあり、これを参考にお子さまの読解力が判断でき、買うべき本が見つかるそうです。
「英語 難易度別リーディングガイド」にも、「なか見検索!」のできる本が紹介されていますので、参考にされてはいかがでしょうか。
2. YL とは?
2003年に、古川昭夫さんによって始まったSSS英語多読研究会が、日本人英語学習者向けに「本の読みやすさ」を表したのが「YL(Yomiyasusa Level)」です。
Penguin Readers や、Oxford Reeding Treeなどの”Graded Readers”をはじめとした洋書に、YL0.0?YL9.9の100段階の読みやすさで表しています。
YL0.0に近づくほど英文の単語数が少なくなっており、絵のみでできているお話はYL0.0と表されます。
英語多読研究会SSSのサイトには、YL別の洋書リストがあるので、そちらを参考にしてみてください。
3. DRA とは?
Developmental Reading Assessmentを省略したもので、Learning A-Zで紹介されている”Benchmark Books, Leveled Books”の読書に必要なレベルを見極めるために活用されている評価方法です。
これにより、学習者が、現在どのくらいの英文を読むことができるのかをチェックすることができ、どの本から読みはじめたら良いのかを決めることができます。
チェックは、専用の用紙に「間違いに気づかないまま読み続けてしまった単語」や「読み間違いに気づいて訂正できた単語」などを記入することができ、子どもの読む力を細かく測ることができます。
「読めなくてとまってしまう」「読み間違い」など特定のミスをエラーとし、読み上げた単語数の何%正確に読めたのかを割り出すことができます。
数値の表し方は、以下の通りです。
95~100% 1人で読むのに苦労しない文章
90~94% 読むのに補助が必要な文章
89%以下 学習者にとって非常に難しく、読みながら不快に感じてしまう
段階的に読み進められるシリーズ本の紹介もしています。
ぜひご覧ください!
- この記事を書いた人
 ESL club編集部
ESL club編集部
ESL clubは、英検1級・TOEIC 900点・TOEFL iBT 95点以上のバイリンガルによる完全マンツーマンレッスンが特徴の英語スクールです。
小学生で英検2級合格多数、大学受験の英検活用から海外留学準備まで、様々な生徒に英語指導を行っています。そんな日々の指導から得られた知見をブログで発信しています。