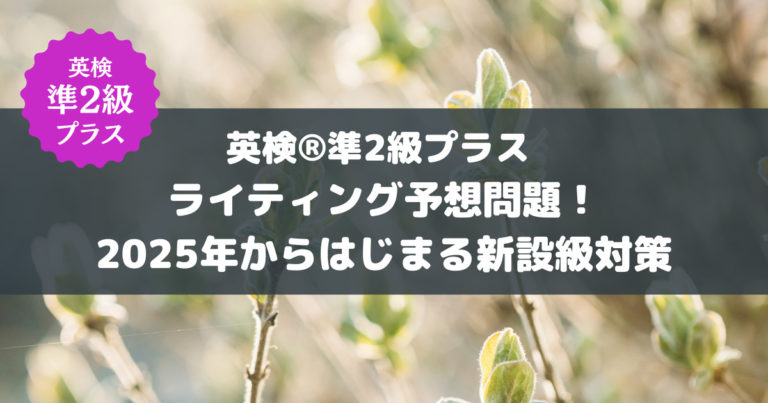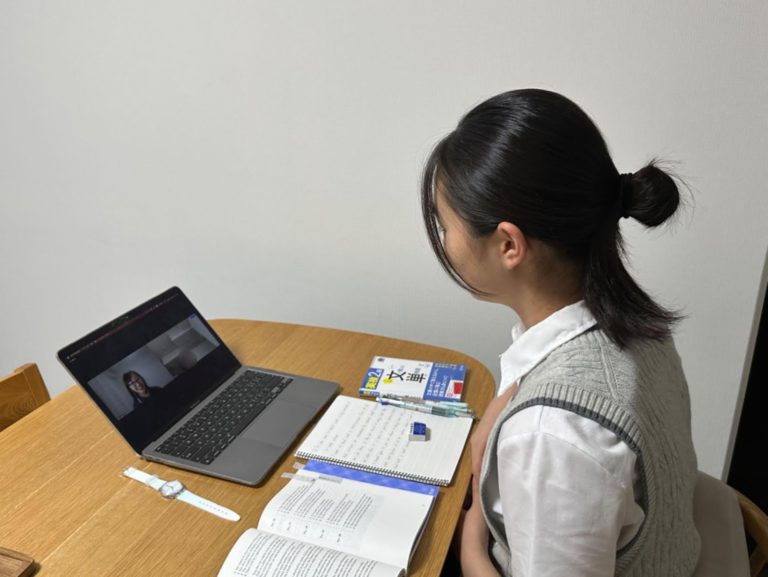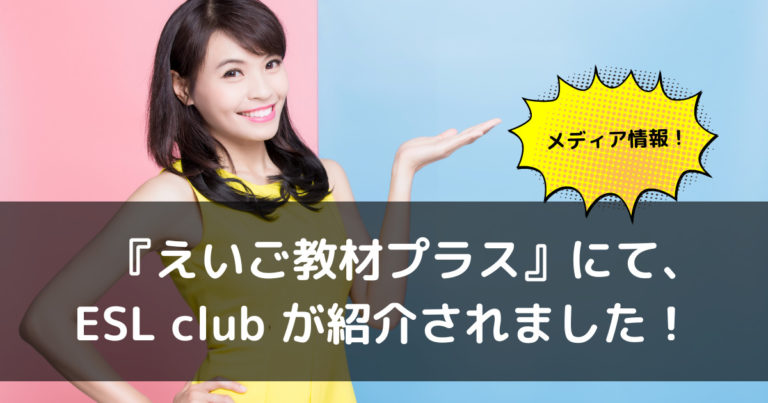-
 「英語 x 私」で広がるストーリー
「英語 x 私」で広がるストーリー バイリンガル講師インタビュー|「英語を使って人生の可能性を広げる楽しさを知ってほしい」
帰国子女としての経験から日本の英語教育に疑問を抱き、中高生の頃から「こうやって教えたらもっといいだろうな」と考えていたというESL club講師のA.M先生。レッスンではそんな気づきを抱いていたからこそ思いつく工夫を日々実施し、生徒の成長へ導いています。 今回はESL club講師として活躍するA先生に、生い立ちや英語スキルを伸ばした方法、英語学習に対する考え方などをインタビューしました。 -
 メディア情報
メディア情報 【メディア情報】 『帰国生のミカタ』にて、ESL club が紹介されました!
帰国生向けのメディア『帰国生のミカタ』の「国内学習塾」にESL club が掲載されました。 ぜひ、ご一読ください。 -
 メディア情報
メディア情報 『週刊SingaLife』の別冊『教育ガイドブック2025春』号にESL club が掲載されました!
シンガポールのフリーペーパー『週刊SngaLife』の別冊『教育ガイドブック2025春』号にESL club が掲載されました! ぜひ、ご一読ください。 -
 英検準2級プラス
英検準2級プラス 英検®準2級プラスライティング予想問題!2025年からはじまる新設級対策
英検準2級プラスのライティング予想問題をまとめました。準2級プラスは2025年度からスタートする新しい英検試験。ライティング問題がどんな形式か不安に向けて、本記事では準2級プラスのライティング予想問題を3問取り上げ、模範解答とともに解説します。 -
 受講生エピソード
受講生エピソード 小学4年生で英検®2級に合格!海外からオンライン受講でESL clubを選んだ理由と魅力とは
今回は、シンガポールの日本人学校に通う小学4年生のDさんにインタビューしました。 小学3年生の夏にESL clubのオンライン校に入会し、英検4級・3級レベルの学習をはじめたDさん。 大好きなサッカーの練習に打ち込みつつ、学習開始からわずか10か月という短期間で英検3級・準2級・2級に次々と合格、現在は英検準1級の学習に励んでいます。 サッカーと両立しながら、講師も驚くスピードでスキルアップした秘密はどこにあるのでしょうか。Dさんとお母さまにお話を伺いました。 -
 受講生エピソード
受講生エピソード 小学生で英検準2級に合格し中学受験に成功!帰国子女のお母さまからみたESL clubの魅力とは
今回は、中学1年生のMさんにインタビューしました。 小学校4年生の終わりにESLclubオンライン校に入会し、英検4級の学習から始めたMさん。小学生のうちに準2級に合格し、取得した英検を活用して中学受験も成功させました。現在は、学校生活や部活動と英語学習を両立させながら、英検2級取得を目指しています。 帰国子女であるお母さまならではの視点もふまえて、詳しくお話を伺いました。 -
 メディア情報
メディア情報 【メディア情報】 『STUDY CHAIN』にて、ESL club が紹介されました!
『STUDY CHAIN』にて、ESL club のインタビュー記事を掲載していただきました。 ぜひ、ご一読ください。 -
 受講生エピソード
受講生エピソード 「英語は得意じゃなかった」はずが英検2級に一発合格!講師も驚く急成長の理由
今回は、高校1年生のTさんにインタビューしました。 中学1年生の入会当初は通っていた中学校で英語の補講を受けた経験もあるというTさん。 英検5級の学習からスタートし、約5か月後には英検5級と4級をW受験のうえ、5級は満点、4級もほぼ満点合格。その後も、英検3級、準2級、中学3年生の秋には2級に、すべて一発合格し、ほぼ不自由なく英語でコミュニケーションを取れるようになった現在、目標である英検準1級の受験に向けて、順調に対策を進めています。 元々英語が得意なわけではなかったというTさんは、ESLclubを活用してどのように実力を伸ばしていったのでしょうか。 -
 受講生エピソード
受講生エピソード インターナショナルスクールとの両立で英検2級合格!帰国子女は英語ができるを乗り越えた秘訣
今回は、国内の私立中学校に通うY.Yさんにインタビューしました。 Yさんは、小学校を卒業するまでの期間を海外で過ごしてきた帰国子女です。 非英語圏の日本人学校、日本の小学校、中国のインターナショナルスクールと家族の転勤に伴い学校が変わっています。 「うちの子は帰国子女なのに英語力ができない」と悩む方や、インターナショナルスクールでの英語学習に課題を感じている方は、ぜひ参考にしてみてください。 -
 メディア情報
メディア情報 【メディア情報】 『えいご教材プラス』にて、ESL club が紹介されました!
『えいご教材プラス』にて、ESL club が紹介されました! ESL clubの口コミ・評判3選【英検2級を狙えるオンライン英会話】