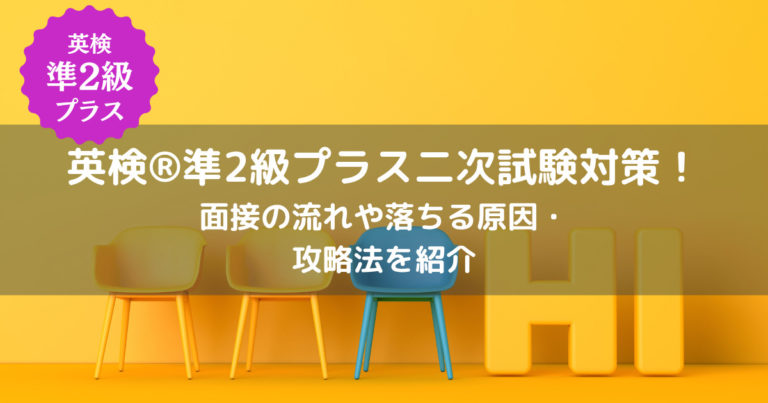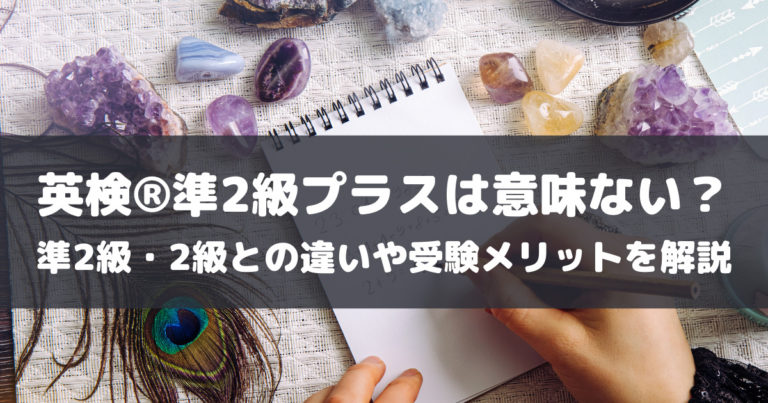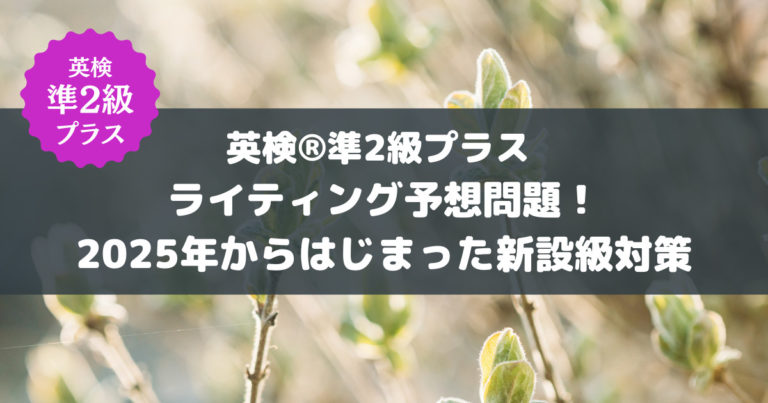-
 英検準2級プラス
英検準2級プラス 英検®準2級プラス二次試験対策!面接の流れや落ちる原因・攻略法を紹介
英検®準2級プラスの二次試験で合格するためのコツは、面接の流れや頻出質問に対する回答の「型」を知り、練習を重ねることです。 英検準2級プラスの面接・二次試験を会話実例つきで詳しく解説します。二次試験に落ちる原因と対策、おすすめの勉強法、押さえておきたい裏ワザのほか、合格対策に使える練習問題も紹介します。 注意すべきポイントを押さえて、英検準2級プラス面接・二次試験の合格を目指しましょう。 -
 メディア情報
メディア情報 『週刊SingaLife』の別冊『教育ガイドブック2025』秋号にESL club が掲載されました!
在シンガポール日本人向けフリーペーパー『週刊SingaLife』の別冊『教育ガイドブック2025秋』号にESL club が掲載されました! ぜひ、ご一読ください。 教育ガイドブック2025秋 デジタル版 -
 子供のための英語・英会話教育
子供のための英語・英会話教育 目標は「小学生で英検2級合格」!英語学習のつまずきも経験値に変える秘訣とは?
今回は、ESL club渋谷校に通う小学5年生のMさんとお母さまにインタビューしました。 小学2年生でESL clubに入会し、英検4級からスタート。小学4年生のときに英検準2級に合格し、現在は英検2級合格を目指して英語学習を続けています。 その過程で不合格も経験しましたが、悔しい体験を乗り越え、合格をつかみ取ってきました。 つまずきさえも経験値に変える秘訣は、どこにあるのでしょうか? -
 子供のための英語・英会話教育
子供のための英語・英会話教育 英検®準2級プラスは意味ない?準2級・2級との違いや受験メリットを解説
「英検®準2級プラスは意味がない」と感じていませんか? 英検準2級プラスは決して「意味がない」資格ではありません。しかし2025年度から新設されたばかりの英検準2級プラスについて、英検2級や準2級との違いや受験メリットが分かりにくい、と感じる方も多いでしょう。 この記事では、英検準2級プラスに合格するメリットや、英検2級・準2級との違い、受験におすすめのケースなどを解説します。 -
 「英語 x 私」で広がるストーリー
「英語 x 私」で広がるストーリー バイリンガル講師インタビュー|K先生「教える」ではなく「引き出す」指導で英語学習をサポート
エチオピア・アメリカ・オランダの3か国での海外経験を活かし、ESL club講師として活躍するK.N先生。穏やかで親しみやすい人柄で、生徒から自然に英語を引き出す指導力の高さに定評があります。 英語を「教える」よりも「引き出す」ことを重視しているというK先生は、レッスンにどのような工夫を凝らしているのでしょうか。 今回はK先生に、海外経験や習得した英語が役立った実体験、英語の指導方法などをインタビューしました。 -
 「英語 x 私」で広がるストーリー
「英語 x 私」で広がるストーリー バイリンガル講師インタビュー|「英語を使って人生の可能性を広げる楽しさを知ってほしい」
帰国子女としての経験から日本の英語教育に疑問を抱き、中高生の頃から「こうやって教えたらもっといいだろうな」と考えていたというESL club講師のA.M先生。レッスンではそんな気づきを抱いていたからこそ思いつく工夫を日々実施し、生徒の成長へ導いています。 今回はESL club講師として活躍するA先生に、生い立ちや英語スキルを伸ばした方法、英語学習に対する考え方などをインタビューしました。 -
 メディア情報
メディア情報 『週刊SingaLife』の別冊『教育ガイドブック2025春』号にESL club が掲載されました!
シンガポールのフリーペーパー『週刊SngaLife』の別冊『教育ガイドブック2025春』号にESL club が掲載されました! ぜひ、ご一読ください。 -
 子供のための英語・英会話教育
子供のための英語・英会話教育 英検3級合格&英語スピーチコンテストで全国大会出場!楽しく英語学習を続ける秘訣とは?
今回は、中学2年生への進級を控えたMさんにインタビューしました。 小学5年生の終わりにESL club オンライン校に入会し、英検4~5級レベルから英語学習をスタート。小学6年生で英検4級合格、中学1年生で3級合格と、着実にステップアップしてきました。 英検取得だけではなく、英語のスピーチコンテストにも前向きに取り組んでいるMさん。楽しみながら英語学習を続けてスキルアップする秘訣を、Mさんとお母さまに伺いました。 -
 英検準2級プラス
英検準2級プラス 英検®準2級プラスライティング予想問題!2025年からはじまった新設級対策
2025年度からスタートした英検準2級プラスのライティング予想問題をまとめました。ライティング問題がどんな形式か不安に向けて、本記事では準2級プラスのライティング予想問題を3問取り上げ、模範解答とともに解説します。 -
 受講生エピソード
受講生エピソード 小学4年生で英検®2級に合格!海外からオンライン受講でESL clubを選んだ理由と魅力とは
今回は、シンガポールの日本人学校に通う小学4年生のDさんにインタビューしました。 小学3年生の夏にESL clubのオンライン校に入会し、英検4級・3級レベルの学習をはじめたDさん。 大好きなサッカーの練習に打ち込みつつ、学習開始からわずか10か月という短期間で英検3級・準2級・2級に次々と合格、現在は英検準1級の学習に励んでいます。 サッカーと両立しながら、講師も驚くスピードでスキルアップした秘密はどこにあるのでしょうか。Dさんとお母さまにお話を伺いました。